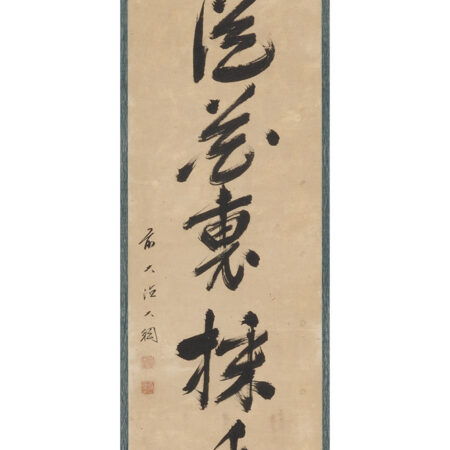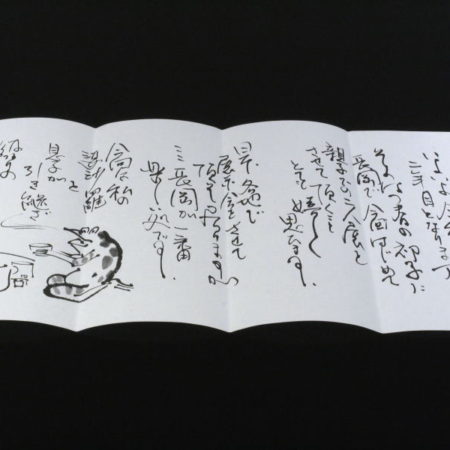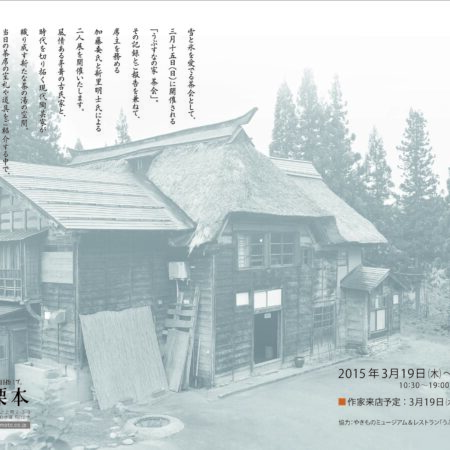木村展之 陶展
2007年1月
2007年2月
特別企画展「陶のかたちⅣ」~現代陶の奇蹟~ ■加藤委■木村芳郎■鈴木徹■三原研■若尾経
2007年3月
市野雅彦 陶展
2007年4月
佐藤和次・日比野正明 二人展
2007年4月
不窮斎 高野宗陵 竹工展
2007年5月
金井正 陶展
2007年12月
名物裂展 ~数寄の極みと現代の織技~
2007年6月
深川萩 助右衛門窯十四代 新庄貞嗣 陶展
2007年7月
四代常山襲名記念 常滑 山田常山 陶展
2007年8月
20年目の感謝を込めて 現代工芸奉仕市
2007年9月
李朝 永岡泰則 陶展
2007年10月
寺垣外窯 杉本貞光 陶展
2007年10月
備前 大澤恒夫 陶展
2007年11月
京都 三代 中村秋峰 陶展
2007年12月
名物裂展 ~数寄の極みと現代の織技~
2007年12月
佐渡 何代窯 本間勲 陶展